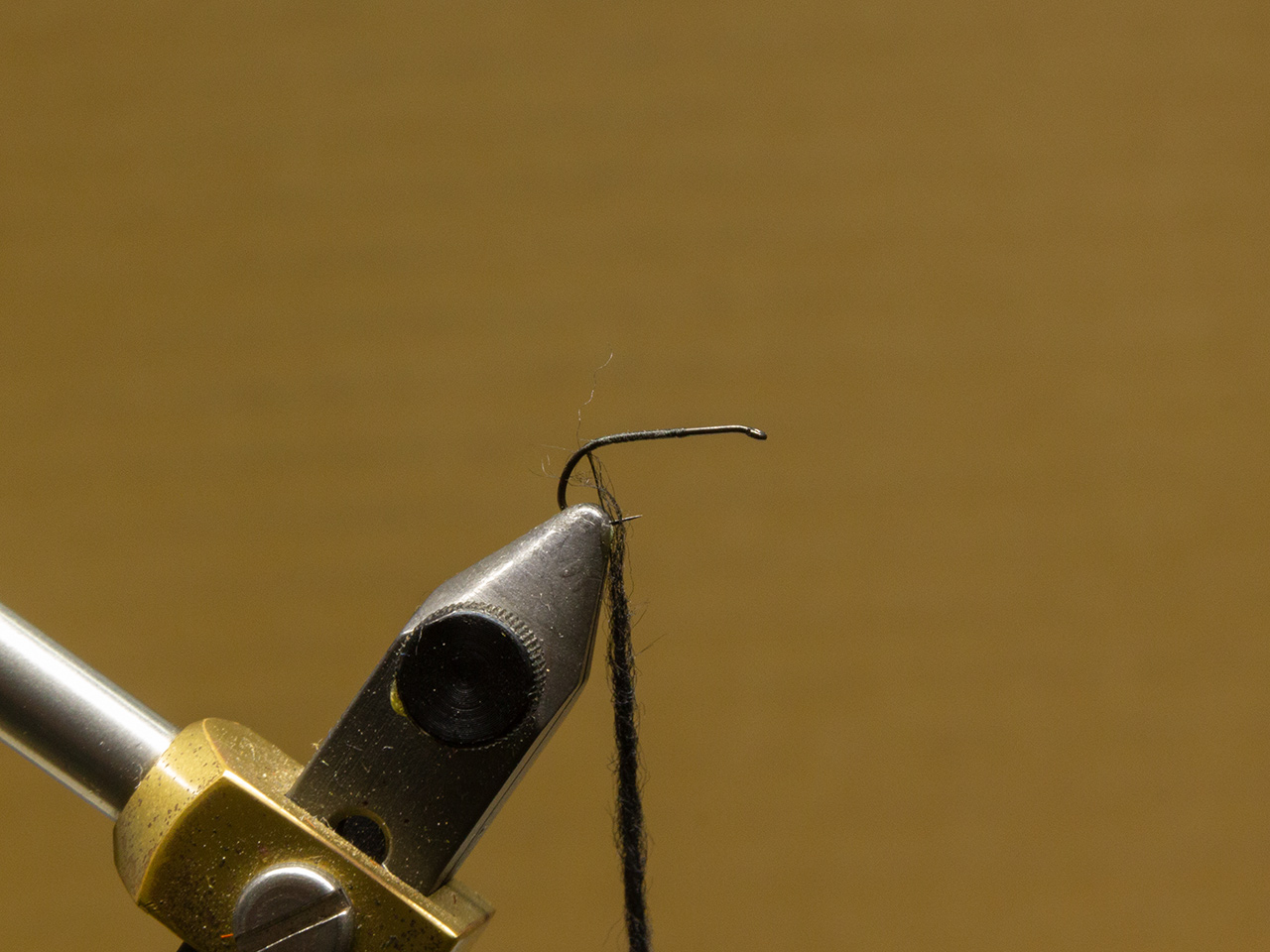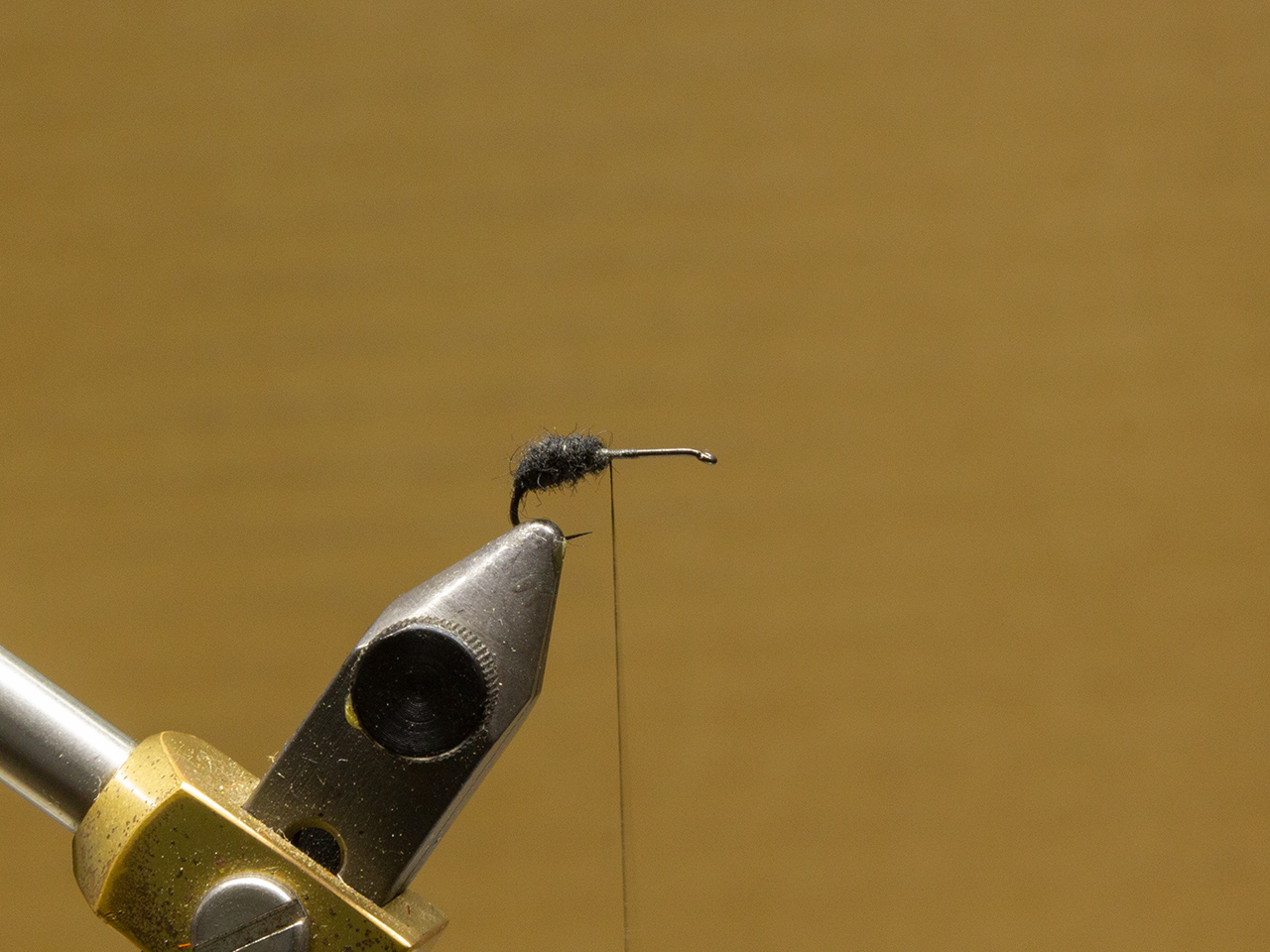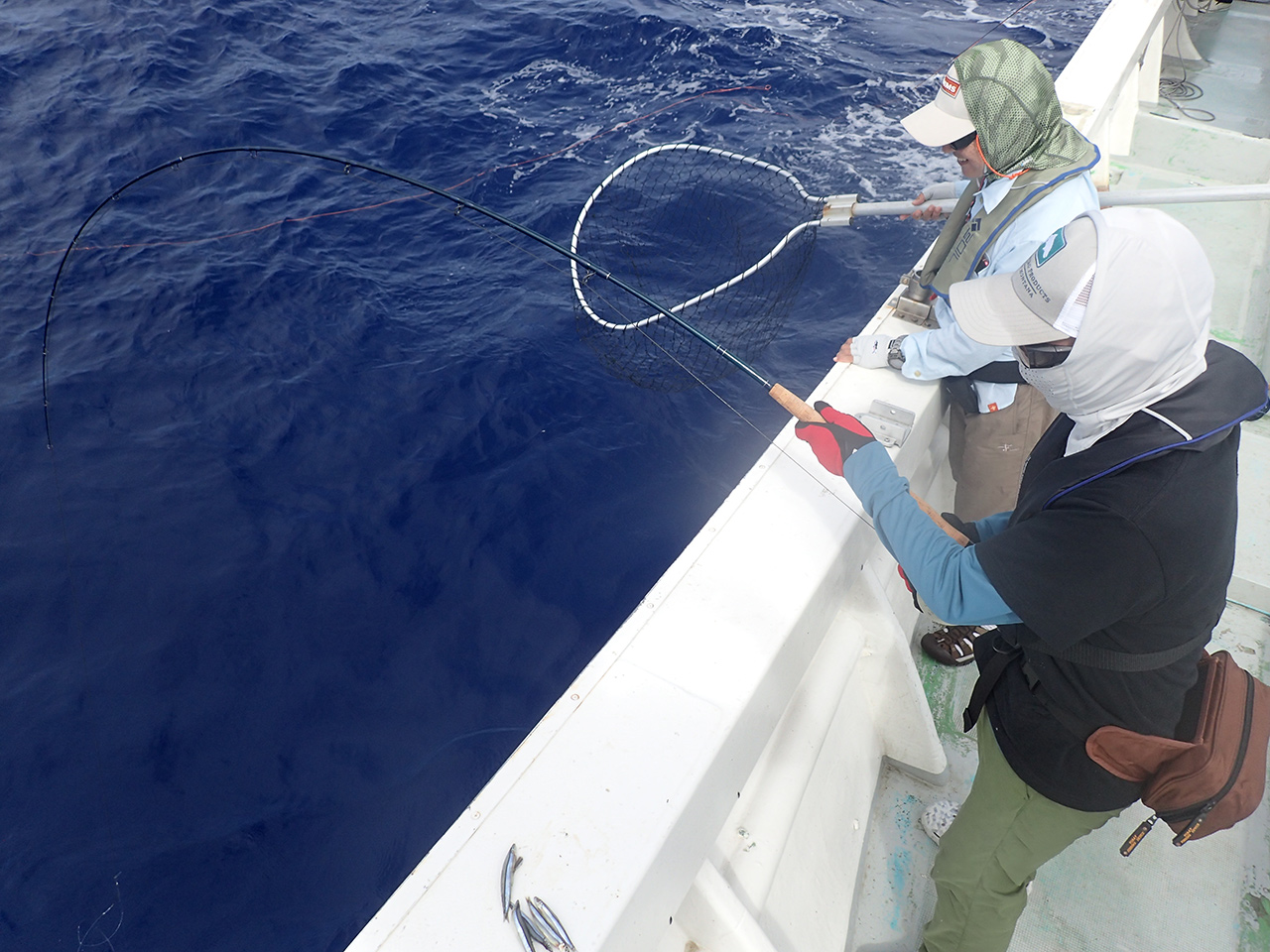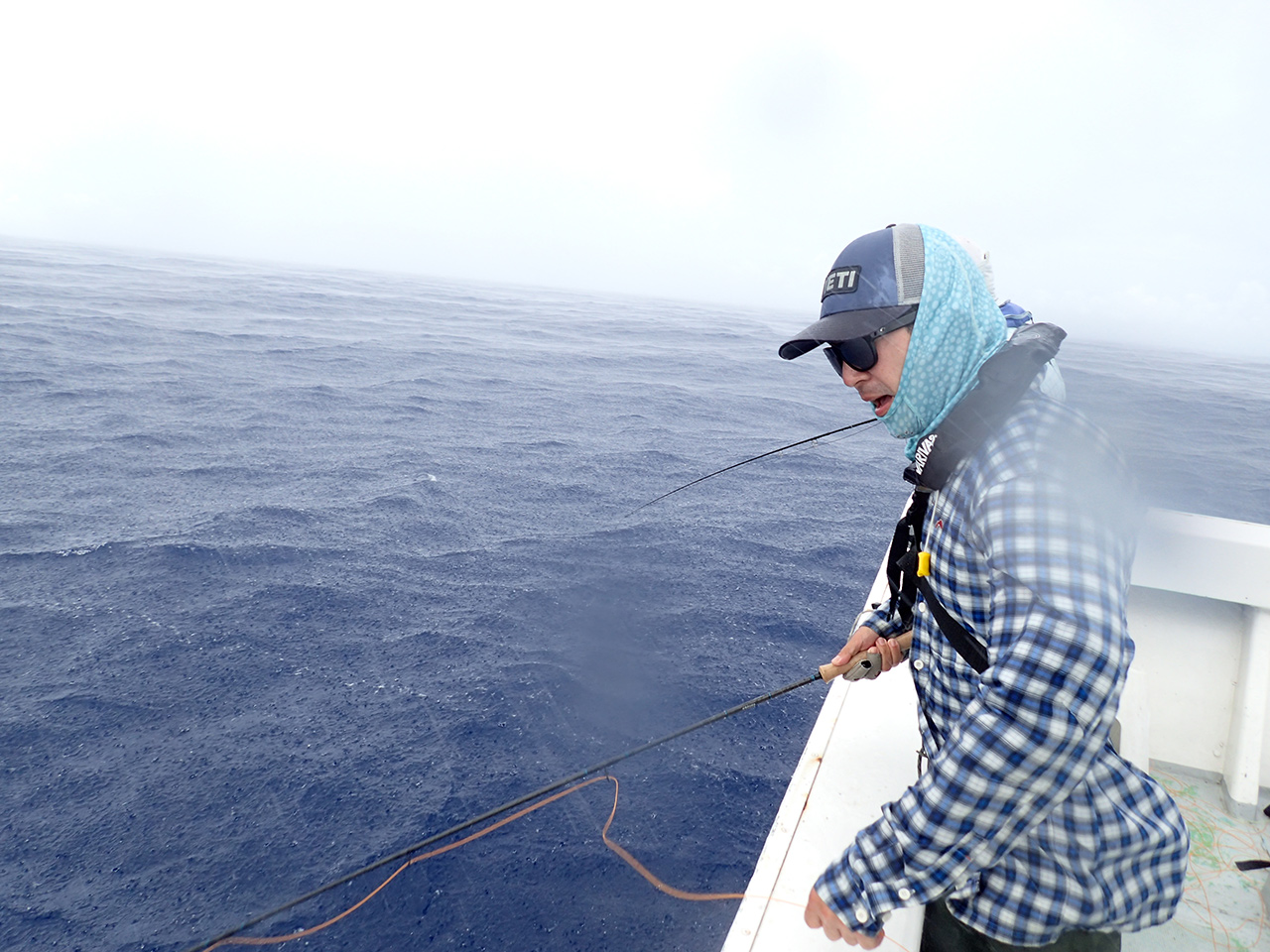最近私が思い悩んでいる事は、イワナが昔よりも釣れない事。関東近県で釣りをされている人は私以外にも感じている事じゃないかな? つい十年前だったらイワナパラダイスだった場所が、今はイワナに変わってヤマメやアマゴに変わっている事が多いのです。これに気づき始めたのはここ3〜4年の事。
最初は台風や大雨が多いからかとも思っていたけれど、ヤマメやアマゴはしっかりと生息しているので、単に生息域がさらに標高の高い所にしか居なくなっちゃっている気がします。やっぱり温暖化なのかな、皆さんはどう感じてますか? あと20年もすると標高1,000m以上でないと生息していない、あるいは関東では釣れないなんてことにならないかちょっと心配。
イワナは僕らフライフィッシャーマンに取っては癒しの魚。ヤマメはフライパターンが合うまでツンデレなのに反し、イワナの反応は予想通りの行動をしてくれる。特に源流部のイワナは少し外れたキャストしても、最初の一投であればフライを見つけると躊躇なく食いついてくれる嬉しい奴。正面から見るとカエル顔でなんとも愛らしい私を癒してくれるアイドル的なお魚なんです。
先週はそのイワナを釣りに新潟へ行きましたが、なんとも消化不良な状態で終わったので今回は私のホームリーバーに近い川へ馳せ参じました。ご存知の通り昨日の予報は午後から土砂降りなので午前中勝負。その場所は平日でも車が3〜4台は止まっている人気のスポットだけれど、そんな予報じゃ誰も来ないよね。朝6時半からゆっくり独り占めデス。
結果を話せば、やっぱり歩いても歩いてもイワナが釣れないんです。そんな中、後半のとある場所で、遠い記憶の情景と今キャストしたフライが流れていくのを見てハタと思い出した。確かこの岩陰から出てくるなと。ゆっくりと浮上した大物はこの渓流で初めて見る最大級で、頭は物凄い幅がある。ゆっくりと浮上した大イワナは何の躊躇もなくパックリと私のフライを咥え込んだ。
してやったり〜!
と言いたい所ですが、何と私アワセ切れしました、ティペットは6X。魚のサイズに対してのアワセは自分なりに熟知している筈なのに、突然「本番ですよ。」と言われると、思った様に体が反応しないのは歳のせいなのでしょうか。強烈なアワセをモロに受けてもがいている厳ついソレは、私の足元でグリングリンするので慌ててランディングネットで救おうと手を伸ばすも間に合わず、淵の奥深くへと消えていきました。まさしくこの川の主イワナ、40センチはあったかな。
ちなみに昨夜見た夢は、この光景がそのまま悪夢の様に繰り返されるのでありました。
あぁ悲しきリアルな失態。今日の私にイワナの話は禁句です・・。
いつもならば車止めからしばらく歩いて入渓するけれど、今回は30分だけ歩いて入渓。しかし最初の1時間はな〜んも反応なし(正確には最初にも大失敗をしております)。なのでしばらくは良い場所だけ叩いて上を目指します。 いつもならばポツポツ釣れる場所が全く反応なし(チビはいたけれど)。歩き始めて1時間半が過ぎたところでようやく反応が出始めた。でもこの場所ははっきり言ってイワナ君の住処なんですよ、君。 一旦釣れ始めると、水深が浅かろうが深かろうが、ヤマメが好きな流速からは必ず反応がある。しかしここは関東では人気のスポットなので食いそびれた魚を二度流ししても全く反応なし。フライを変えて時間を掛けても反応が薄いのは知っているので、さらなる上を目指します。 ヤマメの活発なエリアが過ぎて暫くするとまたパタっと反応がなくなる。いわゆるそこまでが「竿抜け」のエリア。最上流でもなく下流部でもなく、一見釣れそうもないエリアだけを皆さんがすっ飛ばしていくから、その200mだけが物凄い反応でした。ただし、水深がメチャ浅く雨もあってか、魚はほとんど浅い開きにいたので、河原を歩く微々たる音がする度に、魚が逃げ回る姿を多数確認しました。こんな場所であなたは忍足ができれば上出来です。 いつまで上がってもヤマメ三昧。ちなみにこの場所にヤマメの放流はされていないので天然繁殖。パーマークも他の渓と比べても独特。それにしてもイワナいないなぁ・・・。 ヤマメちゃんは慣らした様に6寸半から7寸半ばかり。本来はヤマメの方が好きなんだけれど、これだけイワナが釣れないとどうしてもイワナの顔が見たくなり上を目指す。 最終的に少しだけ水深のある場所の巻き(水が巻いている所)でようやく一本ゲット。イワナはこの一本のみです。でその後は予報通りの土砂降りで退散です。今回はイワナ求めてかなりの上流へ来てしまったので、退渓して車へ戻るのに1時間半掛かってしまいました。さて、来週はどこへ行こうかな?なんて考えてる暇はありません。この週末は南へ遠征でした・・・。