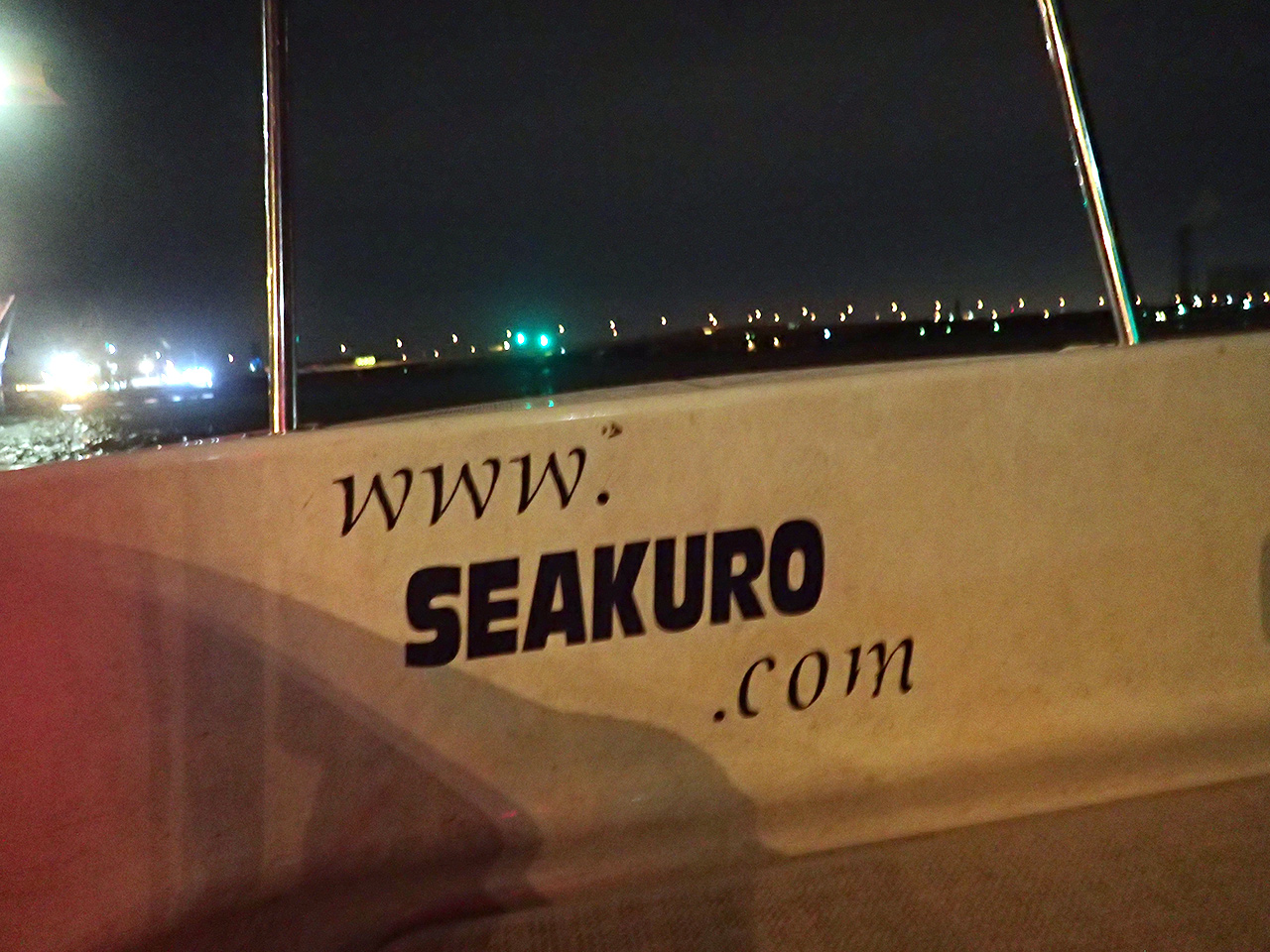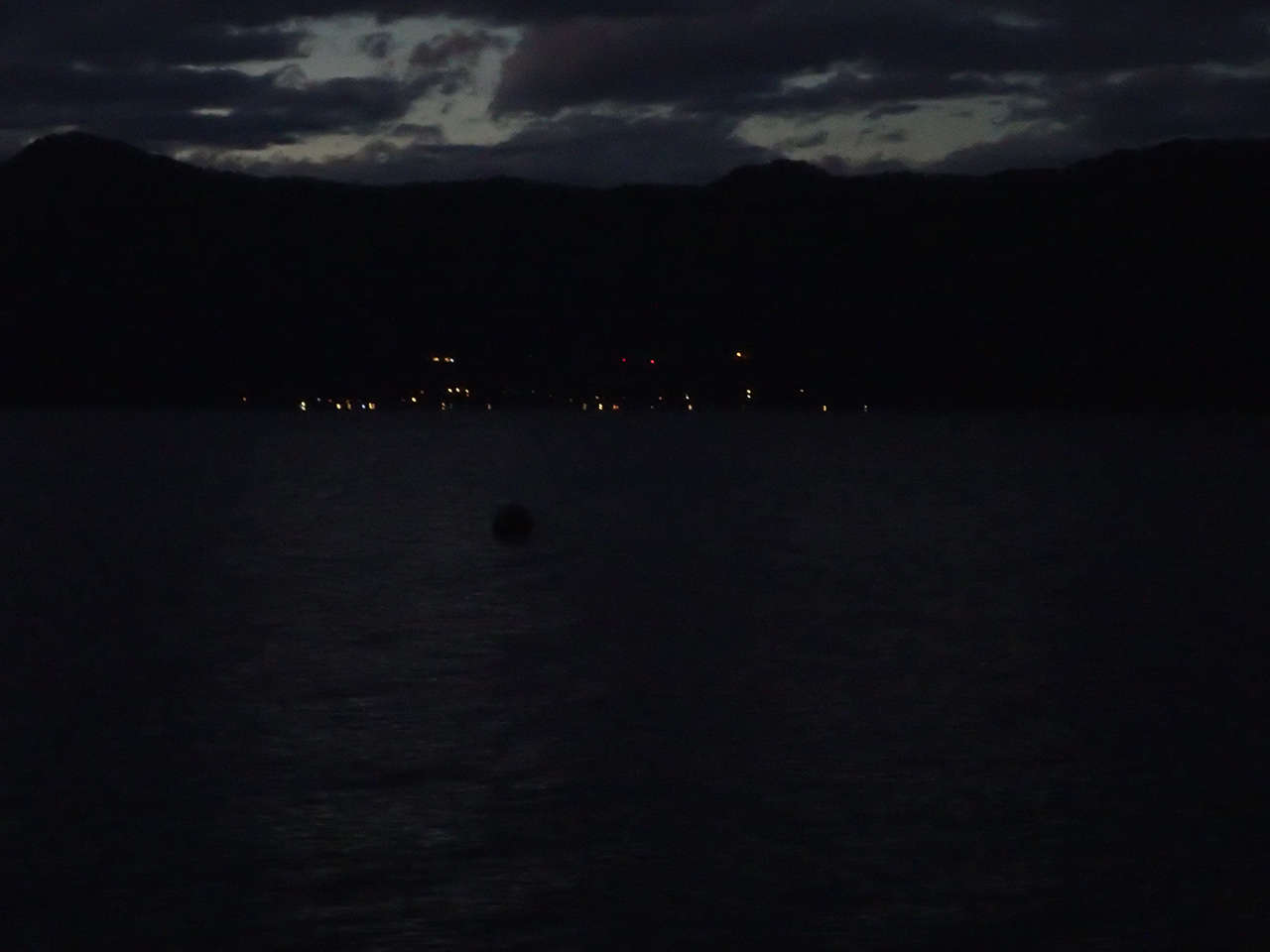昨日は朝練(朝霞ガーデンでフライフィッシング)の後にキャスティングスクールを行ったのですが、渓流のオフシーズンに入った事もあり、多くの方に参加頂き大盛況でした。フライ業界の行先を悲観しているこの業界ですが、皆さんの熱量がある限り僕らは絶滅せずに生き延びられそうです。
さて、その朝練でマーヴェリックさんからセントリックをお借りしました。モデルは904/4・905/4・906/4・907/4の4モデル。このうち905/4は以前のブログで紹介したので、それ以外のインプレッションと実際に魚を釣った感想を書いていきます。
今回、違う番手を含めて振った総合的な感想はやっぱりラディアンの後継機種というイメージではなく、別の新たなジャンルを作ったと思われるシャープさがあります。今回のキャスティングスクールで触れた多くの方々の印象は「Gルーミス風」と言われてましたので、その言葉からそのシャープさが伝わるでしょう。
ただこのロッドを実釣で使ってみてわかった事は、通常は硬いロッドといえば、ロッドの先しか曲がらずショートレンジの投げにくさが際立つのですが、6〜7番でも近距離でロッドの曲がりは得られるので、80年代のハーディグラファイトっぽいアクションにも感じられます。そしてもう一つ際立つのは尋常じゃない軽さ。どのモデルも感覚的には9フィートを振っている感覚はなく、8フィートかと錯覚するのです。今回お借りしたデモロッドの重さは全て測ってみましたので、ロッドの平均重量として参考にしてみてください。
総合的にこのシリーズは本州の渓流には用無し。北海道・本州の本流・湖・ライトソルトウォーター (フレッシュウォーター用ですが使えます)だと思ってください。また、このロッドはキャスティングのし易さを極めたロッドとも言えますので、釣り味や個性を求める玄人好みの竿ではないかもしれない事を付け加えておきます。
C904/4・9feet 4weight・4pcs(自重:89.51g)
Fine:9フィート5番のインプレッション時にも感じた事ですが、この軽さはびっくりするほど。最近のロッドコマーシャルには良くeffortless(努力知らず)と書かれていますが、このロッドは疲れ知らず(tireless)かな。感覚はまるで8フィート。私が振ってみたところ、ピック&レイダウンだけでフルラインが出ました。面白がってダブルホール無しでトライしましたが、流石にそれではフルキャストは無理。それでもあと2mほどでフルラインというキャスタビリティ。感覚的には物凄く軽くライン番手が軽いにも関わらず、その仕事は6番で遠投という感覚が得られます(風には弱いでしょう)。
近距離〜中距離:前述のように近距離での違和感が少なく、そしてラインの乱れが生じないミドルレンジ。ダブルホールができない人でも、そのラインスピードはビックリするぐらい上がります。とは言ってもこのロッドのお仕事的にはミドルレンジ〜ロングレンジを得意とするロッドだと思います。
中距離〜フルライン:キャスティングアーク(ティップの移動距離)を多くする事で、4番という番手なのに呆気なくフルキャスト。投げている方も努力している感が少なく、ビックリ。今回のお披露目でこの4番とC905/4の人気が二分してました。その理由は今まで5番でやっていた事が全て4番でこなせるという感じ。そしてお魚を釣ってみて思ったのは30cm以下の魚は用無しの大物狙い。だって菅釣りの標準サイズは簡単に寄ってきてしまうんだもの。
Weak:9フィート4番という長さから考えても、関東の渓流ではほぼ使わないだろうと思う。また、20センチ程度の軽い魚だと、魚がジャンプするとロッドの反発が強いので、すぐにバレてしまう感じだった。私はこのロッドを買おうと思ってますが、使用用途は今までやっていた湖のドライフライフィッシング(9フィート5番)をこの4番にシフトダウンしようと考えてます。なぜかって?私もジジイですから、やっぱり一日中振り回して楽なロッドが欲しいのです。
追記:私はこのC904/4を購入しました。湖のドライ用に使っています。
C906/4・9feet 6weight・4pcs(自重:92.67g)
Fine:遠投への憧れがある人にはぴったりなロッド。重りとなる9mのラインさえホールできれば、最小の努力で遠投ができる軽量ロッド。または遠くへ飛ばせる楽しさを教えてくれるモデル。キャスティング練習用と書くともったいない金額なので、湖のトラウト全般からブラックバスやライトソルトウォーターターに至るまで、マルチに楽しんでもらいたいです。私がこのロッドと使うとしたら、遠投が簡単に効くのでシンキングラインの釣りを中心に使うでしょう。またはブラックバスやカマス釣りも楽しんじゃうかな?
近距離〜中距離:6番ロッドの場合近距離というのがあまり必要ではないけれど、このロッドはやはり近距離〜中距離時のキャストに投げにくさを感じません。トラウトではないですが、近距離の釣りを中心とするブラックバスにはかなり向いたロッドだと思います。この番手のグラファイトロッドとしては珍しいですね。
中距離〜フルライン:その軽さも手伝って、最小の努力でラインスピードが得られるロッドだと思います。同じ番手の他のロッドで投げにくさを感じている人には、こんなロッドもあるんだなと思って頂くために、一度は振ってほしいと感じます。
Weak:あまりにも努力が入らない感があるので、長年フライキャスティングをやっている方々から「面白くない。」と言われました。キャスティング練習を一生懸命してそのロッドに慣れながらフルキャストを目指す人にとっては真逆のロッドなので、言っている事はわからんでもないです。しかし、一般の方はその努力が嫌なんですものね。またロッドの粘りは少ないので、実際ブラックバスを釣ってないですが、もしかしたらバレやすいかもしれません。
C907/4・9feet 7weight・4pcs(自重:97.09g)
Fine:7番なのに仕事は8番以上を感じさせるのは、キャスターの負担を感じさせない点からでしょうか。その絶妙なロッドバランスと軽さから、手首への負担が最小現に抑えられている感じを受けました。通常はただ硬いというロッドだと、ロッドから伝わるラインの重さに手首が耐えられず反り返ってしまう方が多いですが、不思議とその重さを抑え込めるのです。これって最新の技術が盛り込まれているせいなのでしょうか?
近距離〜中距離:近距離は必要ないでしょうから、そんなに真面目に振りませんでした。力を入れずにピック&レイダウンだけで、フライラインの半分以上は行ってしまうので、最小限の努力で誰でもフライラインの2/3は投げる事ができるのでしょう。
中距離〜フルライン:流石に7番ですから、ある一定のレベルを超えた人には簡単すぎるフルライン。なのでエフォートレス&タイヤーレス、操作性に関しては全く文句なし。7番でありながら8番の距離を簡単にものにできます。ロッドのパワーは十二分、大物思考のアングラー向き。ロッドのパワーをとても感じるので、私だったら湖のシンキングライン専用ロッド(または川での大物狙いシングルハンド)として使う事でしょう。
Weak:7番だけれどそのパワーはすごい。なのでロッドがちょっとやそっとの魚じゃ曲がりません。ラディアンはティップ側が曲がった更なる荷重でバット側が曲がる感じだけれど、このロッドはティップ側が少し曲がった後はバット側が微動だにしない印象。バーブレスフックを使用して飛んだり跳ねたりする魚を相手にしたたら、すぐにバレちゃうかも?そんなイメージです。
今回のロッドは全て9フィートモデルなのでお店でも一番売れている長さですが、個人的にはこのシャープな硬さと軽さを持っているのであれば、9.6や10フィートモデルも触ってみたいです。
 ラインをロックして思いっきり曲げてみました(C904/4)。ベンドカーブはラディアンよりもスムーズ。グイグイ曲げてもバットの腰砕け感は全く無し。
ラインをロックして思いっきり曲げてみました(C904/4)。ベンドカーブはラディアンよりもスムーズ。グイグイ曲げてもバットの腰砕け感は全く無し。
 軽くチョインと振ったループでこんなにシャープ。ロッドは軽くお辞儀するだけですが、Gルーミスほどティップに寄り切った曲がりではありません。
軽くチョインと振ったループでこんなにシャープ。ロッドは軽くお辞儀するだけですが、Gルーミスほどティップに寄り切った曲がりではありません。
 セントリックはジョイントセクションに赤いティッピング。あまりにも目立たないので、個人的には嫌だったのだけれど、太陽の下に出て初めてこの赤の綺麗さに気づきましたよ、ティンセルの赤だったのね。キラキラと輝いてました。
セントリックはジョイントセクションに赤いティッピング。あまりにも目立たないので、個人的には嫌だったのだけれど、太陽の下に出て初めてこの赤の綺麗さに気づきましたよ、ティンセルの赤だったのね。キラキラと輝いてました。
 シングルスクリューロックだけれど、シリコンのレッドラバーリングを入れる事で緩み留め防止。ロッドバランスを考えて、バットエンド側に重量を持っていきたくなかったのかな?シートフィラーカラーはお好みが分かれるところ。
シングルスクリューロックだけれど、シリコンのレッドラバーリングを入れる事で緩み留め防止。ロッドバランスを考えて、バットエンド側に重量を持っていきたくなかったのかな?シートフィラーカラーはお好みが分かれるところ。
 この写真下には25cmほどのレインボーが掛かっているベンドカーブ。すごく曲がっているように見えますが、魚はほとんどぶら下がっている状態だから、約200gぐらいの負荷が掛かっている曲がり。C904/4とスピードスターのコンビネーションはめちゃくちゃ軽かったです。
この写真下には25cmほどのレインボーが掛かっているベンドカーブ。すごく曲がっているように見えますが、魚はほとんどぶら下がっている状態だから、約200gぐらいの負荷が掛かっている曲がり。C904/4とスピードスターのコンビネーションはめちゃくちゃ軽かったです。