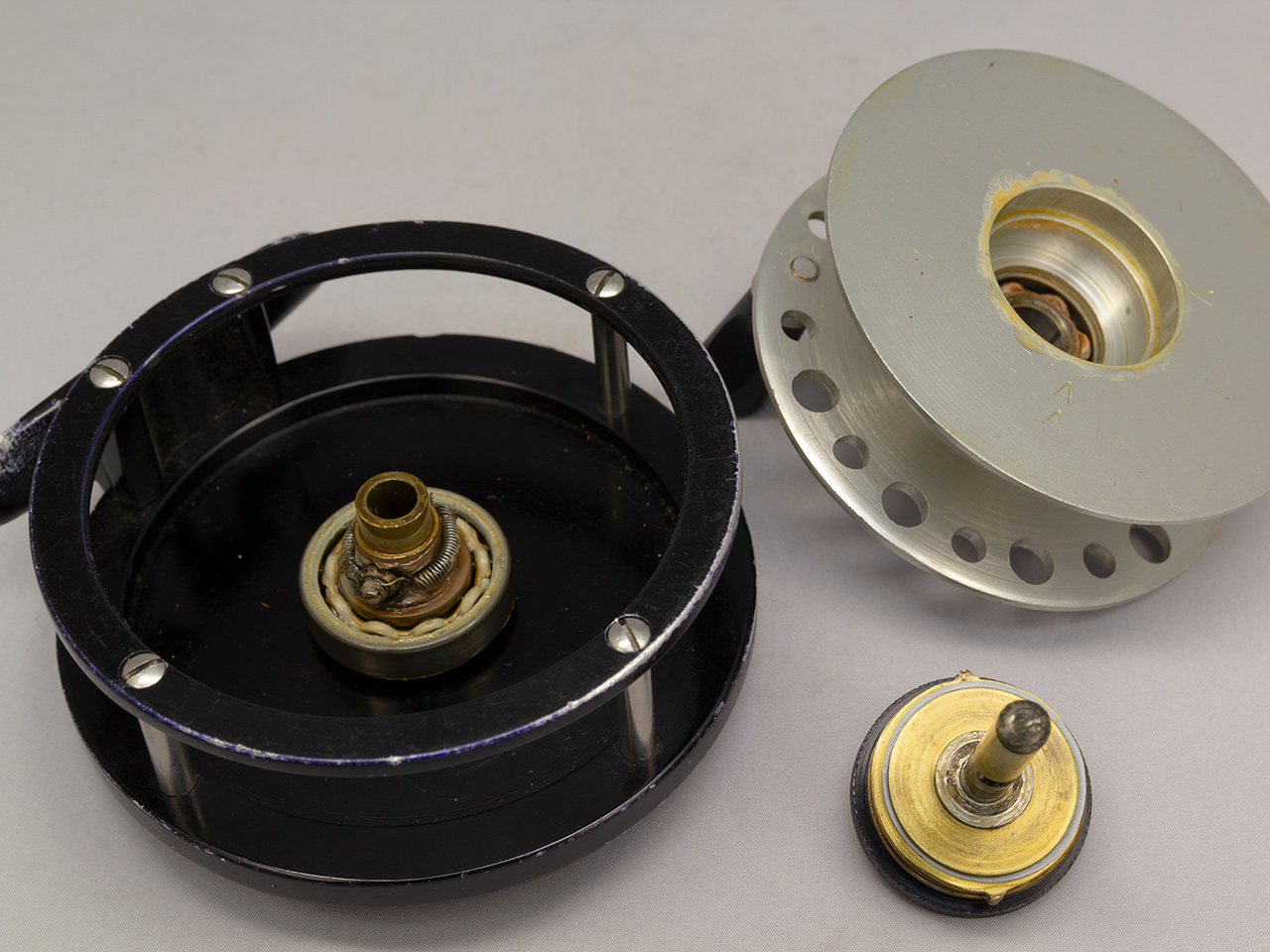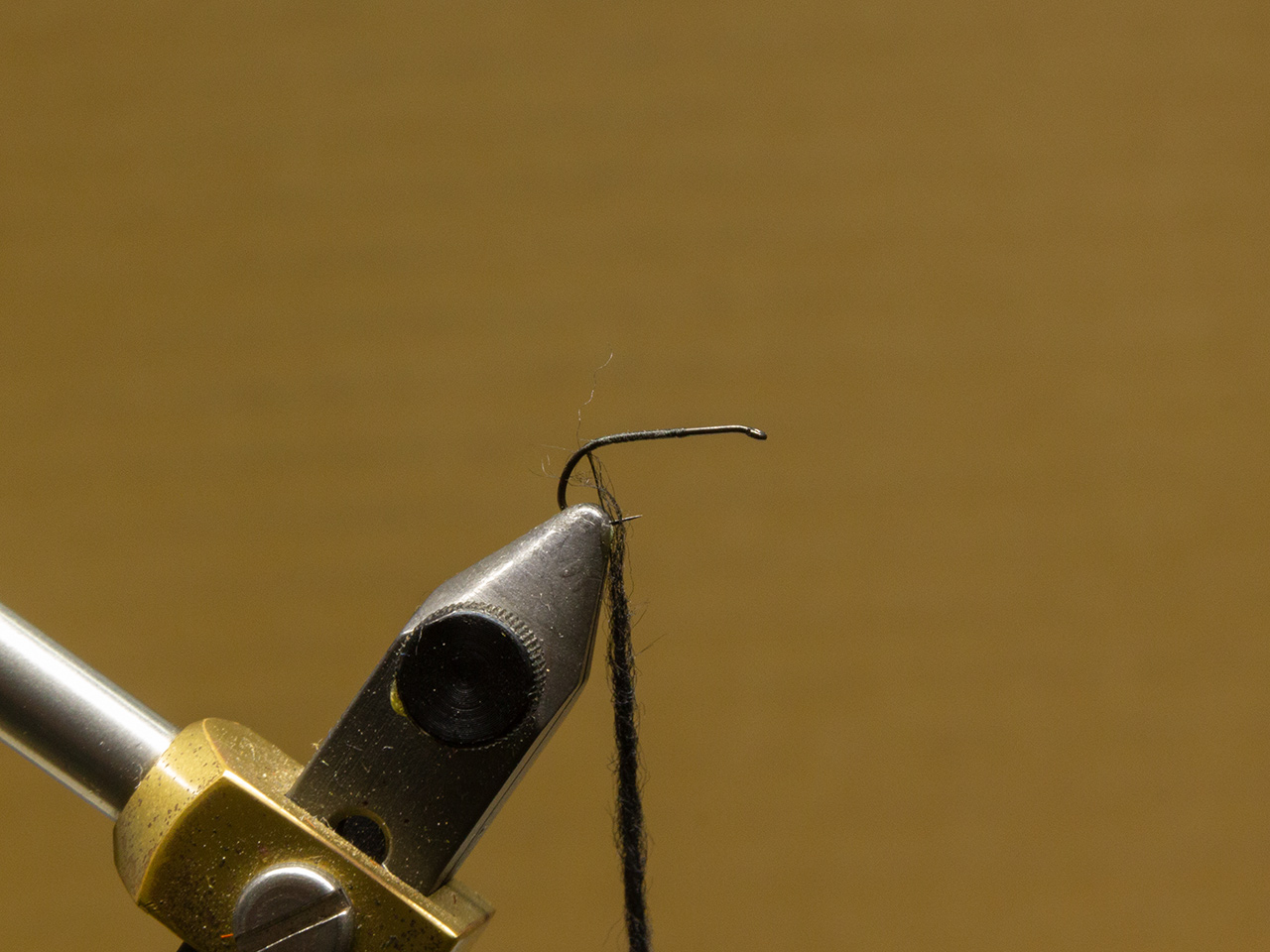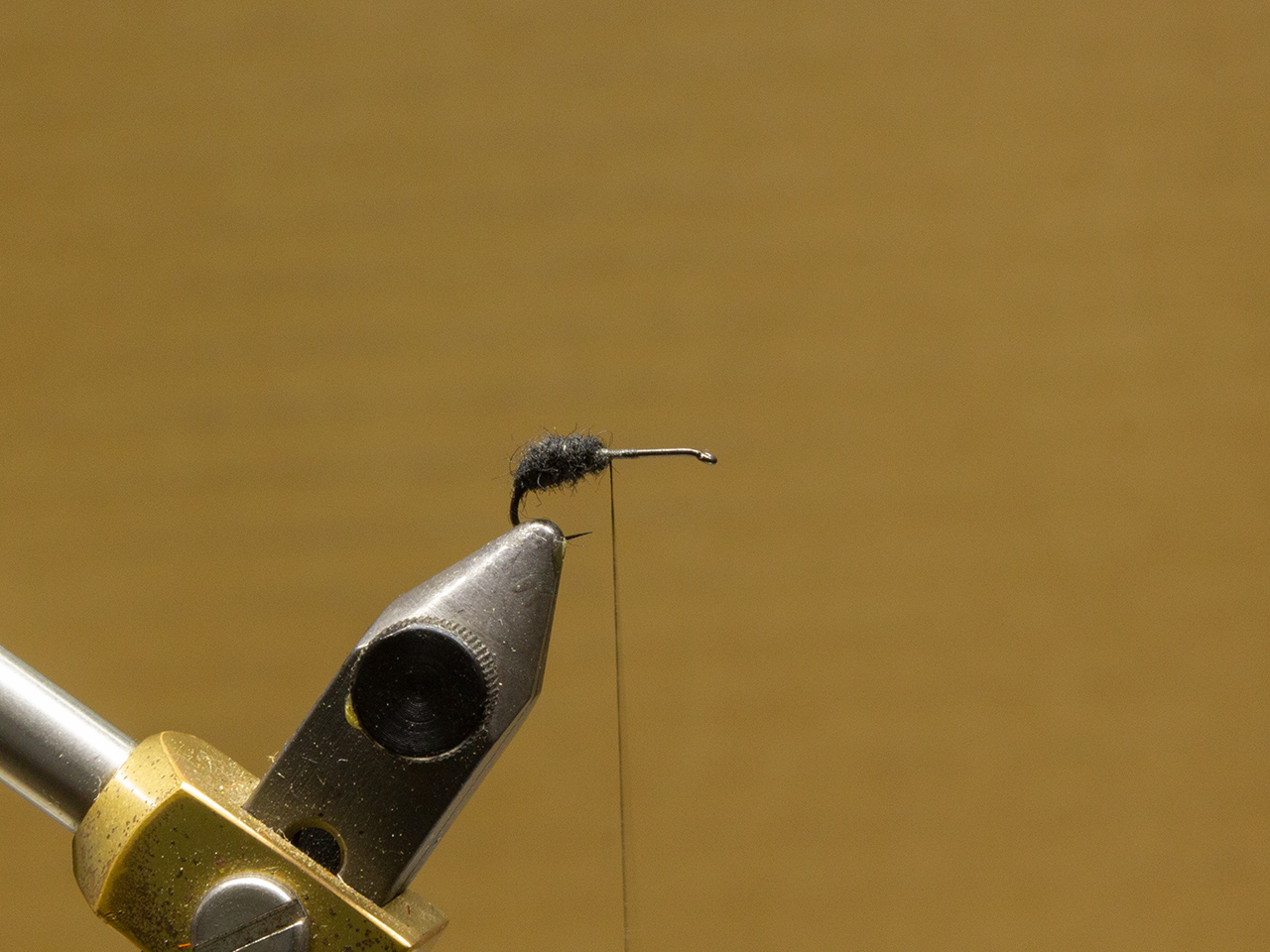2028年春に発売されたSFFS(School Fish Finding System)のキャッチコピーにはこう書いてある。
「魚群はドローンとAIで探す時代。今まで魚群を見つけるのに掛かっていた時間をいとも簡単に省くシステムがついに実現。これであなたはワッチ役をする事なく、アラームの指示と共にすぐにフライフィッシングの戦闘態勢に入れます。」
*釣り用語で言うWatch(ワッチ)とは、鳥山やボイル(魚が捕食して海が割れる状態)を見つけるよう先輩に命ぜられる若者の仕事の事
ようやくこのシステムを手に入れることが出来た私は、沖へ向けて進む船上で付属のドローン8機を解き放った。そのドローンは少しのホバーリングの後に100mほど上昇し、船の四方に散らばって行くのが見えた。それに積まれた機能は魚群の種類、自動追尾、魚群の水深、そしてもちろんGPS機能。さらに追っているベイトの種類まで算出してくれる。
西に飛び立ったドローンから手元のアップルウォッチにこんな情報が送り込まれてきた。
その情報は船長の魚群探知機にもwifiでリンクされており、自動操舵で到着時間を算定する。僕らはその時間を使ってタックルをチェンジし、ナブラ(ボイル)打ちをするのである。
そんな装置があったらなぁ、と思った昨日の微睡んだ時間。若い頃は先輩に「ミヨシ(船首)でお前らが率先して魚を探せ。そうしないと船長のモチベーションが下がるからな。」と言われたっけ。先輩はいつも前日に飲み過ぎて二日酔いなので、目立たぬ場所でグースカ寝ているけれど、僕らが魚を見つけた途端に船首に立ち、一番最初に魚をキャッチするという上下関係。厳しかったけれど楽しかった昔の思い出だなぁ。
と私は夢の中で魚影と闘っていたら船長の声で叩き起こされた。
船長の一言を合図に船上は戦場と化し、夏らしい日差しと相模ブルーに染まったシイラが次々と宙にまうのでした。
結果、そんな未来のシステムよりプロの場数と勘は何よりも凄いものだと感じた、沖上がり(釣り時間の終わり)間際の1時間でした。そんな塩梅なので写真はほとんど撮ってません。イレグイが始まればカメラなんて構える人間なんていないもの・・。
最初に向かった城ヶ島沖のパヤオ。様子を探るために鈎なしのルアーを投げてみるも、潮が悪く小魚さえいない状態。今日の苦戦を感じさせる。 開始して最初はワッチを買って出て船首でずっと魚を探し続けたけれど、4時間以上も続けて諦めモード。私は船長の後ろで不貞寝するのでした。 いくつもの漂流物(ナガレモノ)を叩いても釣れなかったのに、シイラの群れは突然やってくる。船尾左側に見えるあんな少しの笹竹に沢山のシイラが着いているのだから、魚の気持ちは幾つになっても判らない。 まだこの釣りを始めて間もない人たちはずっと竿を降り続け、経験者は夏の行事のように数本キャッチした後は皆のランディングを手伝う連携プレー。 全員がキャッチした頃には余裕も出てきてようやく周りが見え始める人々。こんな大海原で魚が入れ食いになる幸せを、年に一度は味わいたいですね。 今回は釣れ盛ったのは後半の1時間だけ。なので釣りに夢中で魚の写真は雑に写してます(笑) 12番のロッドがこんなに曲がるのですから、サンマスクで隠れて見えない笑みは想像できる筈。しばし歓喜の声が飛び交う時間です。 相模ブルーに染まったこのマヒマヒ(シイラ)をあなたも釣ってみませんか? 道具は少々お高くても、その思い出は一生です。