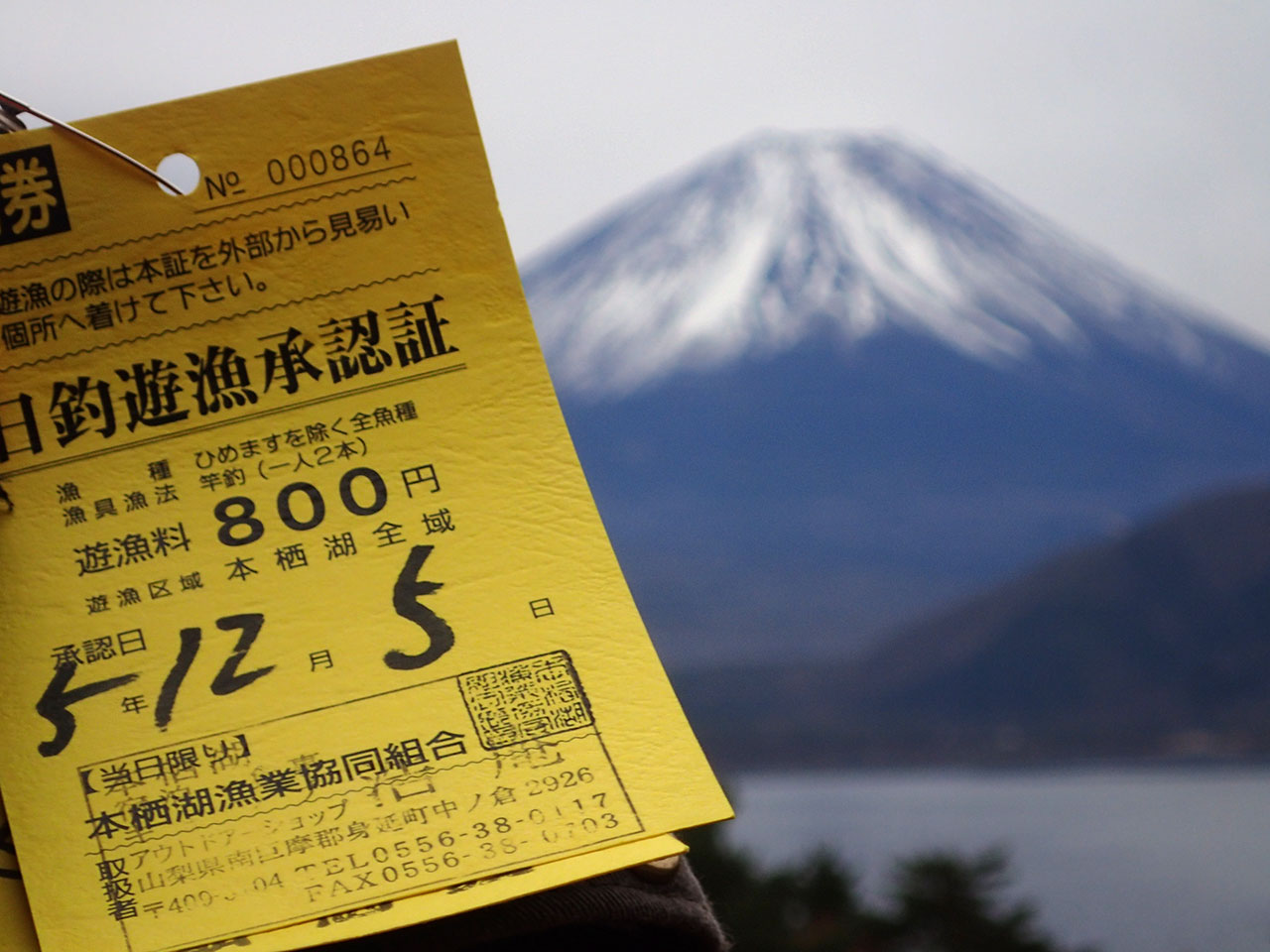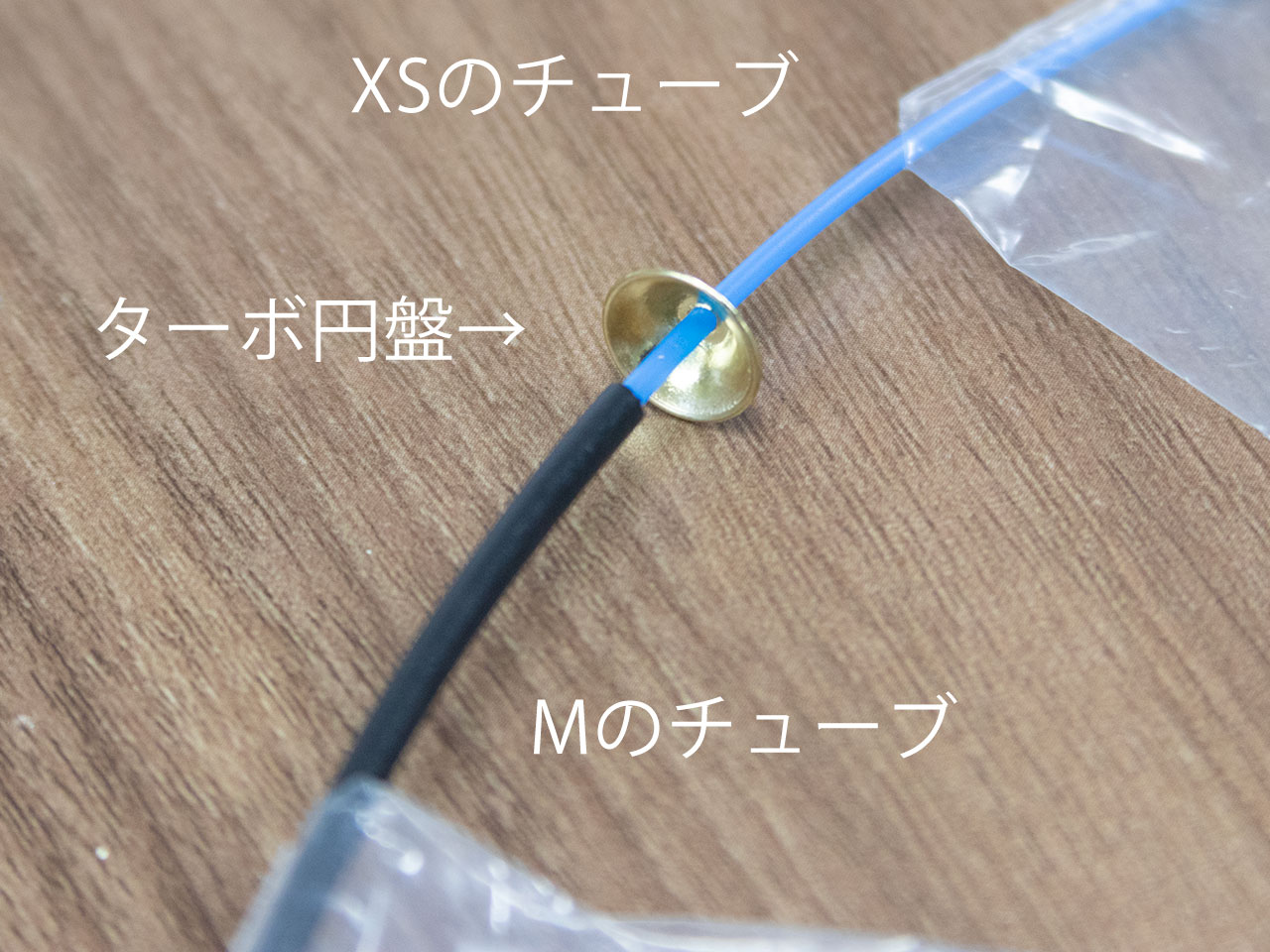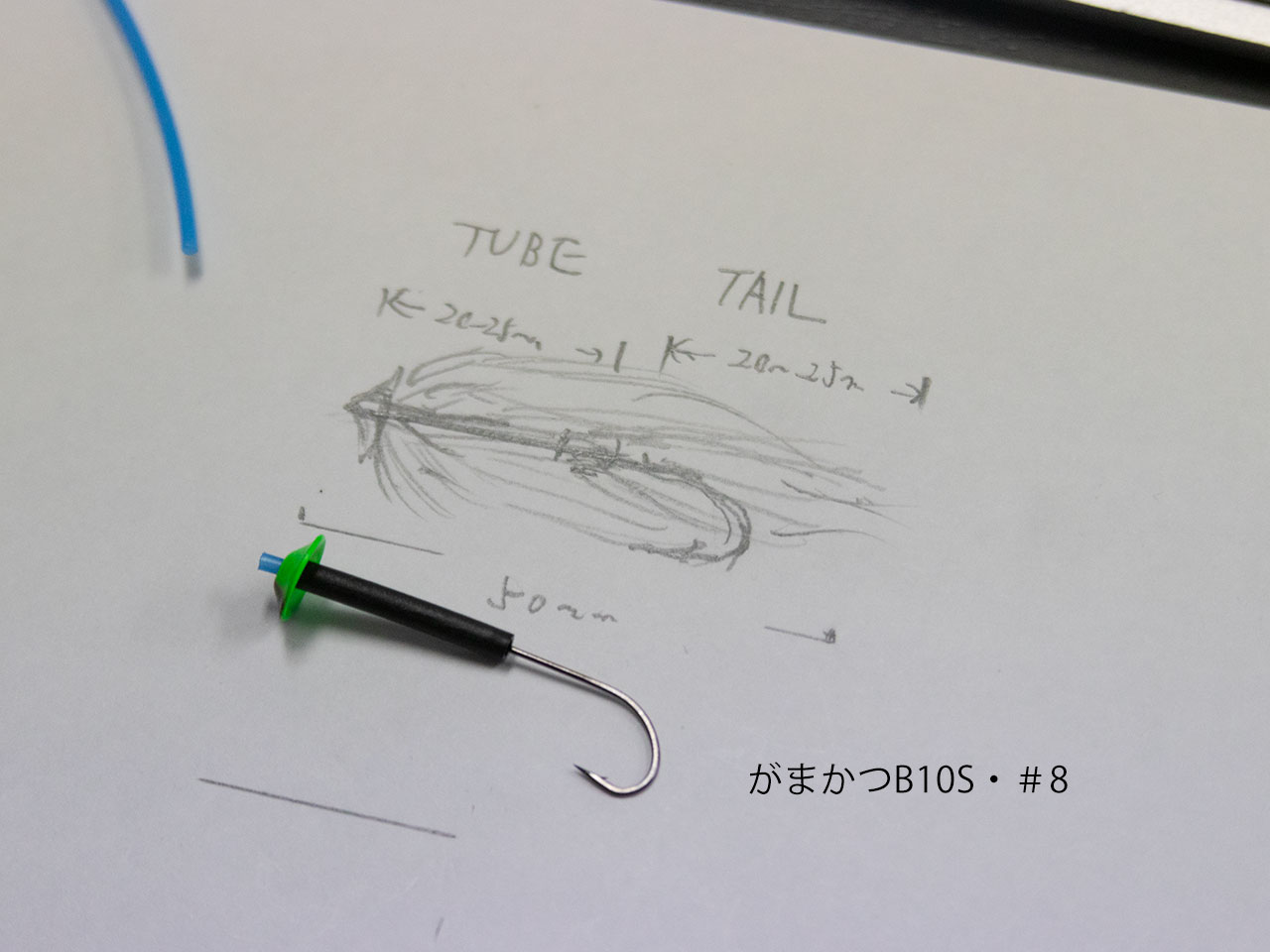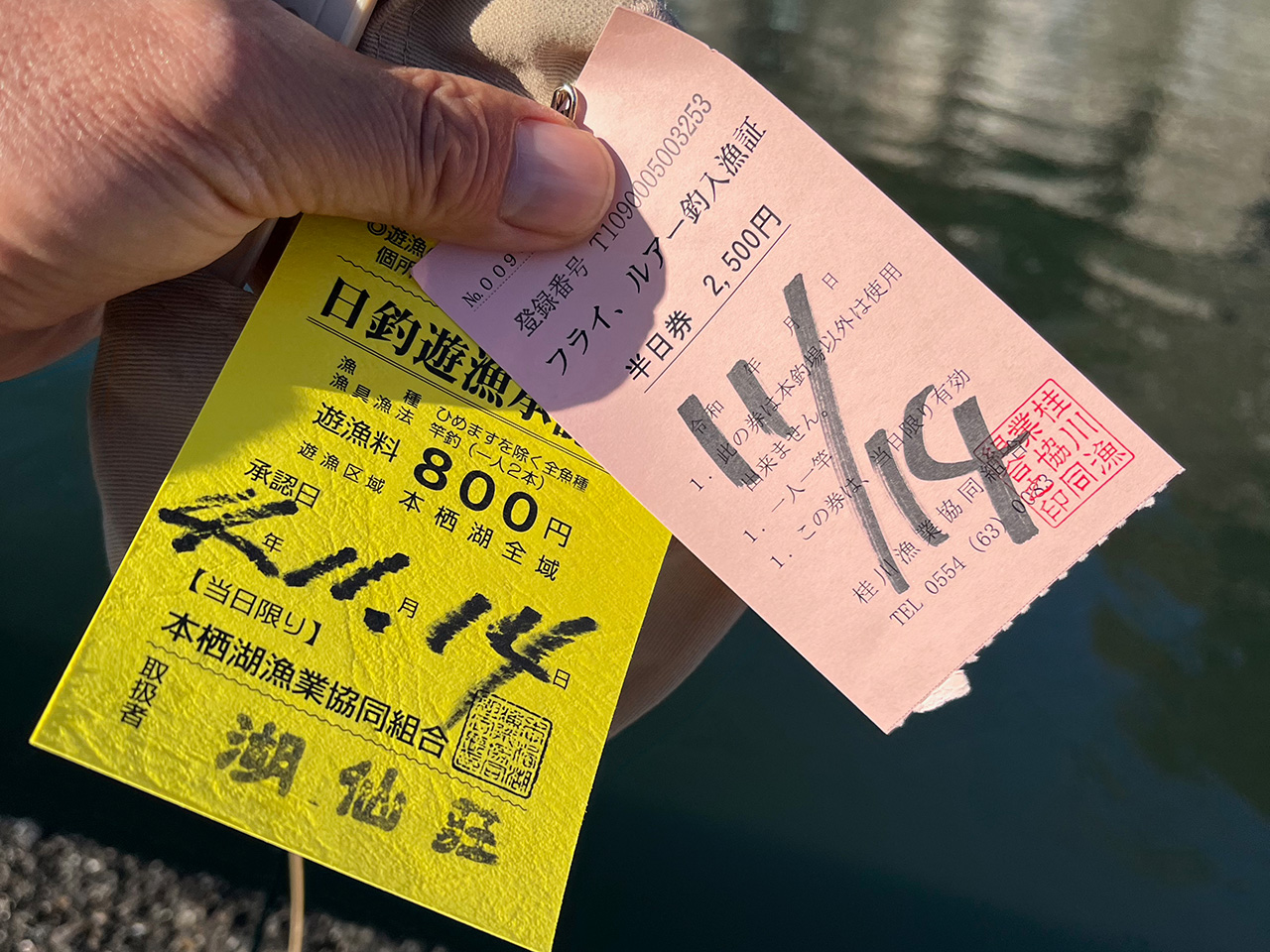先だってのNRX SRよろしく、秋になると新製品のラッシュ。で今回は岩手のロッドメーカーのファーガスの新製品、「Active Hiker」の試投ロッドを借りられたので、そのインプレッションを書いていきます。
その前に余談を一言。ファーガス社長のNくんは、一昔前はハーミットに通う大学生でした。就活が近くなると、「フライ業界で働いてみたい。」なんて言い出すものだから、「趣味を仕事にするのは大変だしビンボーになるから辞めておきなさい。」と私は窘めたのですがこの業界に入ってきました。ハーミットはそもそも店頭販売では学割があり、また学生のうちは「ハーミットで金など使うな。」と、中古で使えそうな物は学生に上げているのです。その本音を言えば、就職したらハーミットへ貢いでくれるだろうというものなんですが、ハーミットに出入りしていたその後の学生たちも順調に育ったのですが、私の意見を制して皆この業界に入ってきてしまうので、当初の目論見とは違い思いのほか回収ができていません(笑)
余談はさておきアクティブ・ハイカーのお話。今回は朝霞ガーデンに持っていき、お客様にも直接振ってもらったり、釣ってもらいながらのご意見もお伺いしたので、それを交えて話していきたいと思います。
このロッドを見る前はフォレストバムのテイストを6ピースにしたものかな、と想像していたのですが別物でした。一番短い7フィート3番は総重量は58.5gとペグ(ジョイント部分のこと)が増えたのにとても軽い。アクションはティップ側で曲がり、真ん中ら辺が少し硬く、バットセクションがグッと曲がるのでミディアムスローアクションと言えます。しかし、ラインを乗せた時の印象はフォレストバムよりもロッドに腰があり、ラインスピードが早いモデルに仕上がっています。
6ピースなので魚をかけた時にペグ部分に硬さが大きく残ってしまうかと思いましたが、思いの外カクカクとはせずに自然なベンドカーブを持っています。ただ、ロッドのミドル部分が硬いので、大きく曲げたときにグリップ側が曲がってくるので、この感覚が好きかどうかは好みが分かれるところでしょう。
f-7003AH/7feet0inch・3weight・6pcs:ロッドバランスがよく、リールをセットした時にちょうどグリップ位置に重さが来るので、キャスティングは軽快。極端にティップが曲がることがない為か、ミドルセクションの硬さによりラインスピードがあるプレゼンテーションができる。
Fine:フォレストバム7フィートモデルより使用レンジが広く使えそうで、中距離でのもたつき(ロッドのラインロードが遅くなるなど)が無い。リーダーとティペットの返りが早いのが印象的で、グラファイトに近い軽快感を持ち合わせている。
Weak:力を込めたキャスティングではグリップからグニャリと曲がるので、人によってはこの感覚が苦手な人がいるかもしれない。遠投は必要ないけれど、フルキャストをするのはかなり難しい。
——-
f-7033AH/7feet3inch・3weight・6pcs:4つのラインナップを見た時に、76の4番を買おうかなと思っていたけれど、実際に振った感じでこのモデルが欲しくなった。私は幅広くロッドを使うので、極端に柔らかいロッドを渡されるとキャストの修正に少し時間がかかるのですが、グラスなのにこのロッドはソレがない。
Fine:フォレストバムで気になっていた、魚を見つけてキャストが力んだ時に生まれるロッドの曲がり過ぎがなく、多少あったとしてもラインから生まれるループがテーリングしにくい。もしくはキャストの状態を選ばす、グラスでありながらかなりシャープなループが生まれる。
Weak:昨今のプログレッシブアクションのグラファイトロッドを振っている人はミドルセクションが硬めのこのロッドを振った第一印象はバットの腰の弱さにアレ?と感じるかもしれない。ただ、ラインを澱みなくロードする能力は優れているので、慣れたら振るのが楽しくなるのではないかと思う。
——-
f-7034AH/7feet3inch・4weight・6pcs:7フィート3インチは3番と4番が存在するが、バット径がやや太くなる程度の違い。同じ長さだけれど4番モデルの方がロッドバランスはややトップヘビーになる
Fine:昔のグラスロッドを振っている感覚で、ティップに感じる重さが自然にキャスティングアークの幅を誘導してループを生んでいる感じが、キャスティングがとても楽しくなってくる。出張の際にどんなヤマメやイワナ、あるいは管釣りでちょっと遊ぶとなったら、力に余裕があるこの4番モデルが良いかな。
Weak:振り心地は私にとっては快適なのだけれど、トップヘビーになった事で持ち重り感を感じてしまう人も多い筈。しかし、トップヘビーのロッドはラインのデリバリーがロッド自体で仕事してくれているので、それをわかって欲しいかな。使用時のロッドバランスの事を考えると、リールは最新モデルの超軽量は使わず、110〜120g位あるリールが良いかも。今回はスピードスター-3+なのでリールウェイトは91グラム位。
——-
f-7064AH/7feet6inch・4weight・6pcs:このシリーズで最大の長さと番手を持つモデル。3番モデルよりもトップヘビーが顕著で、ロッドがラインを運んでいる感が得られるロッド。大きめでバルキーなフライを使う人へのモデル。
Fine:ロッドが仕事すると表現する人が多いけれど、まさしくそんなロッド。所定の位置でロッドストップさえ出来れば、綺麗なループが生まれる4番。73よりも3インチ長いだけだけれど、振り心地は少し穏やかになる。グラスらしさがあり、幅広く楽しめる一本。
Weak:古い人間である私には快適なんですが、グラファイトだけを振り回している方が最初に使うグラスはこれじゃないと思います。その反対にピンピンするグラファイトが嫌でグラスらしい振り心地と釣り味を求める方であれば、コレだと思います。
 メーカーの表記でスモーキーグリーンとされたこのカラーは、ファーガスロッドのカラーの中では一番好きかも。ただ、こういった中間色は釣り休憩の最中に草むら近くにロッドを置くと、竿を探すのが大変なんです(汗)。
メーカーの表記でスモーキーグリーンとされたこのカラーは、ファーガスロッドのカラーの中では一番好きかも。ただ、こういった中間色は釣り休憩の最中に草むら近くにロッドを置くと、竿を探すのが大変なんです(汗)。
 ファーガスロッドはインチは二桁であることを考慮して00インチと表記される。フックキーパーはロッドの下側。グリップ長は全てのモデル一緒で、バットエンドからワインディング(グリップ一番上)までは24センチ。グリップだけの長さは15センチ。魚をロッドに並べた場合、#の当たりが30センチになる。
ファーガスロッドはインチは二桁であることを考慮して00インチと表記される。フックキーパーはロッドの下側。グリップ長は全てのモデル一緒で、バットエンドからワインディング(グリップ一番上)までは24センチ。グリップだけの長さは15センチ。魚をロッドに並べた場合、#の当たりが30センチになる。
 7フィート3番のリールをセットした時のロッドバランス位置。この位置が前(ティップ側)に来るとロッドは重く感じ、後ろ(リール側)に来ると軽く感じます。キャスティングを快適にするためには、自分がロッドを握った位置からグリップ前10センチ程度までが快適です。あなたのリールとロッドのバランスは合っていますか?
7フィート3番のリールをセットした時のロッドバランス位置。この位置が前(ティップ側)に来るとロッドは重く感じ、後ろ(リール側)に来ると軽く感じます。キャスティングを快適にするためには、自分がロッドを握った位置からグリップ前10センチ程度までが快適です。あなたのリールとロッドのバランスは合っていますか?
 私がずっと使っているオービスのCFOIIIをセットした図。リールシートはカップ&リングのスライドバンドタイプ。リングをグッと押し込むことでコルクが締まって止まります。危なっかしく見えますが、ちゃんと止めれば落ちることはありません。
私がずっと使っているオービスのCFOIIIをセットした図。リールシートはカップ&リングのスライドバンドタイプ。リングをグッと押し込むことでコルクが締まって止まります。危なっかしく見えますが、ちゃんと止めれば落ちることはありません。
 お客さんが持ってきたオービスのスーパーファインシリーズ(現行モデルの一つ前)と比べてみる(ピンボケでスミマセン)のは同じ7.6フィート4番。写真ではわかりにくいのですが、オービスの方がずっとバットが太くロッドバランスを考えてバット側に重心を持ってきています。なのでオービスは持った時の印象はとても軽く、そしてグラファイトチックな振り心地。それに対してアクティブハイカーはバットがやや細くスローなので、ロッドの重心がもっと前にあります。そういった場合、リールをやや重くしてロッドバランスをグリップ位置に近づけると、キャスティングが快適になります。
お客さんが持ってきたオービスのスーパーファインシリーズ(現行モデルの一つ前)と比べてみる(ピンボケでスミマセン)のは同じ7.6フィート4番。写真ではわかりにくいのですが、オービスの方がずっとバットが太くロッドバランスを考えてバット側に重心を持ってきています。なのでオービスは持った時の印象はとても軽く、そしてグラファイトチックな振り心地。それに対してアクティブハイカーはバットがやや細くスローなので、ロッドの重心がもっと前にあります。そういった場合、リールをやや重くしてロッドバランスをグリップ位置に近づけると、キャスティングが快適になります。
 魚を掛けた時の曲がり方はこんな感じ。4ピースのフォレストバムと比べるとミドルセクションがやや硬めで、グリップ側が少し曲がります。ベンドカーブを見る限りジョイント部分の硬さはそれほど感じません。
魚を掛けた時の曲がり方はこんな感じ。4ピースのフォレストバムと比べるとミドルセクションがやや硬めで、グリップ側が少し曲がります。ベンドカーブを見る限りジョイント部分の硬さはそれほど感じません。
 ということで私もこのロッドたちで実釣しましたが、ティペットをいくら細くしても切れないのは、グラスのいなす力があってこそ。そしてキャスティングはフォレストバムよりも投げやすく感じます。ちなみに朝霞ガーデンのフライポンドで横(距離が短い方)に向かって投げた場合、3番ロッドで対岸までギリギリでした。なのでこのモデルでフルキャストができる方は達人です。
ということで私もこのロッドたちで実釣しましたが、ティペットをいくら細くしても切れないのは、グラスのいなす力があってこそ。そしてキャスティングはフォレストバムよりも投げやすく感じます。ちなみに朝霞ガーデンのフライポンドで横(距離が短い方)に向かって投げた場合、3番ロッドで対岸までギリギリでした。なのでこのモデルでフルキャストができる方は達人です。