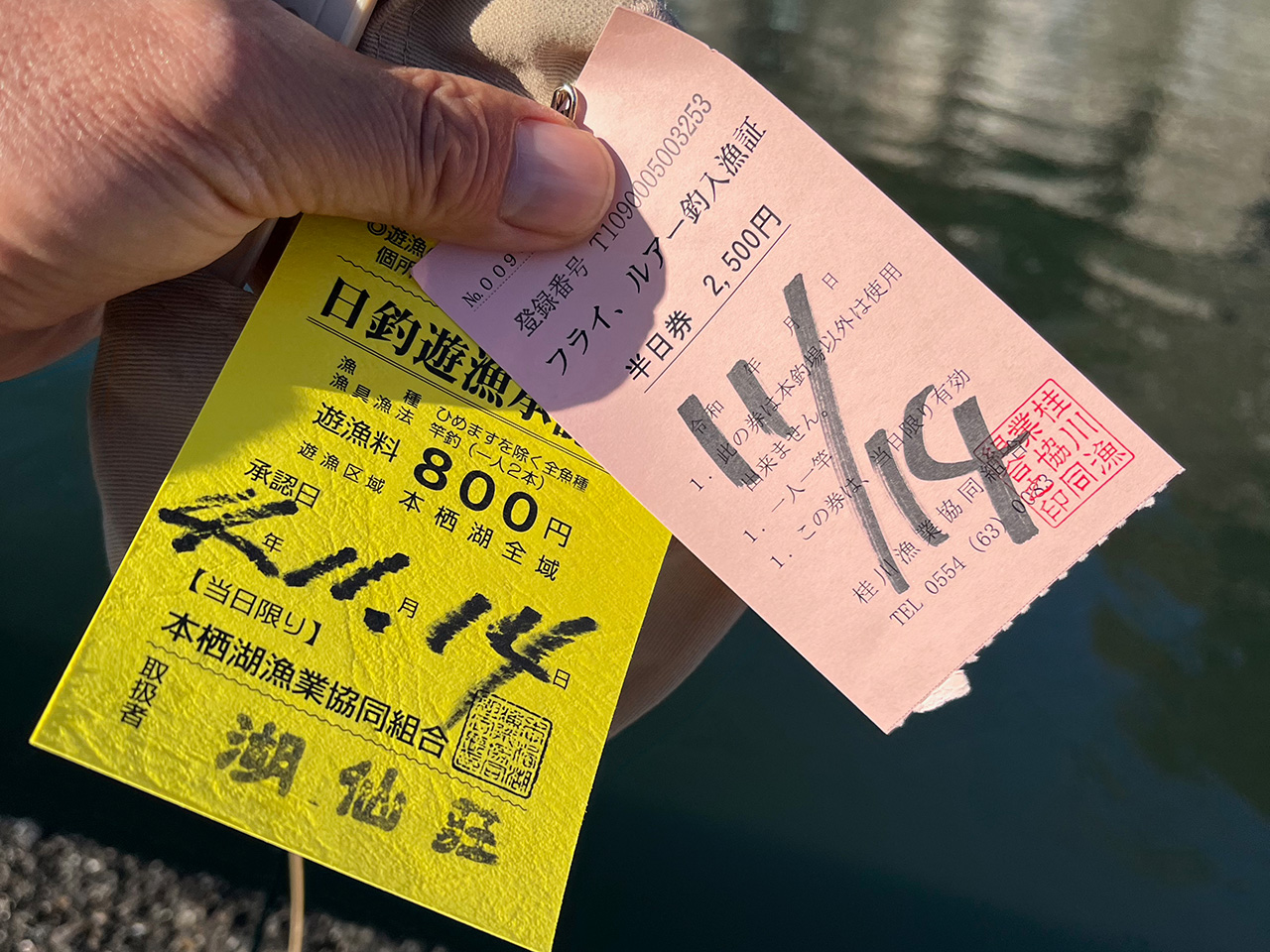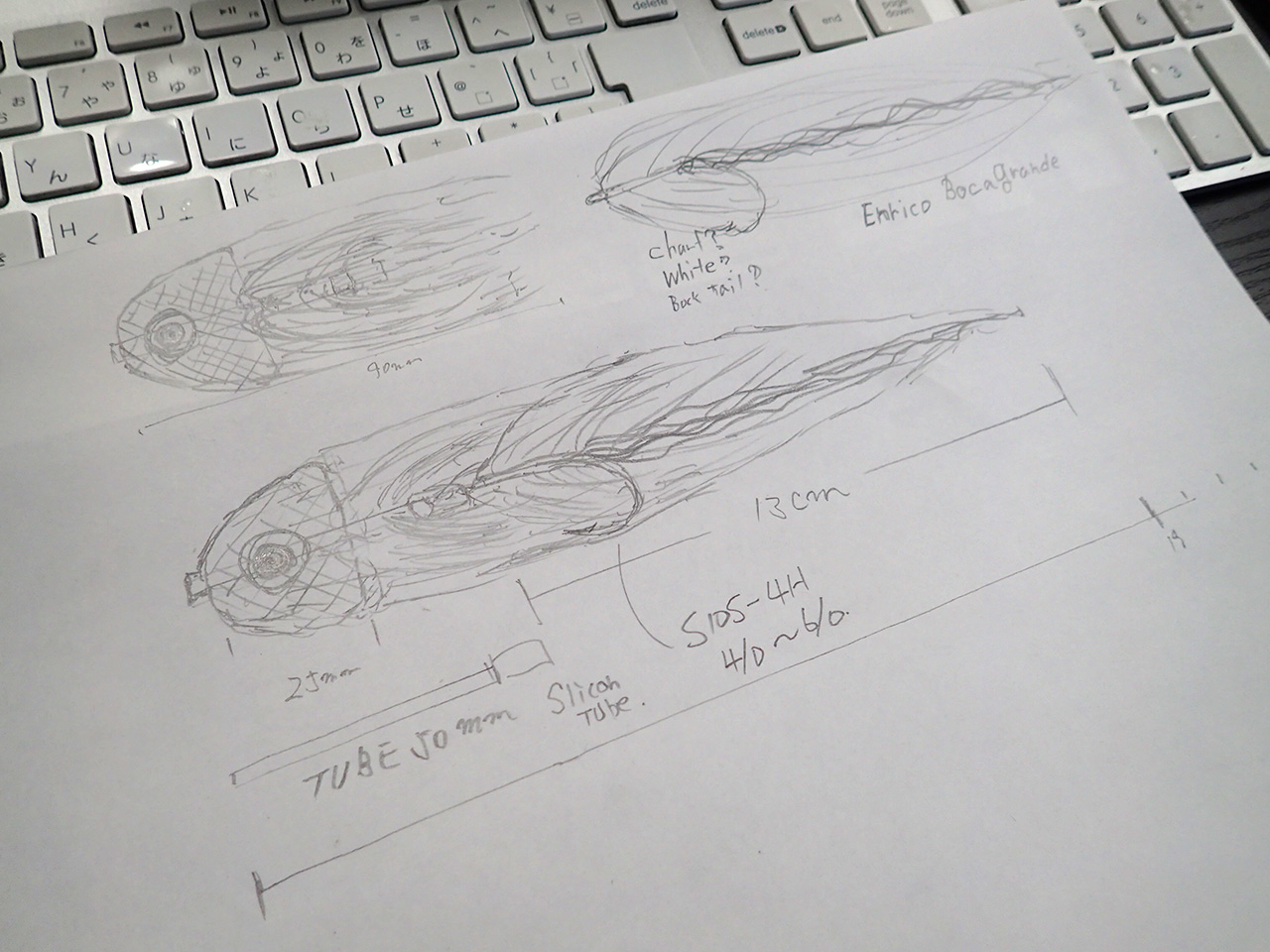もう冬が目の前だというのに、朝3時に起床してマッキーの車を待つ私。今週も例によって本栖湖へ修行へ行ってきたのだけれど、今回はどんな風に本栖湖を攻めているのかをマッキーに伝授する日。そう、ハーミットのお休みである第三火曜定休日は火曜日店長であるマッキーのフライフィッシング研修日なのでアリマス。
なので今回は皆さんにも本栖湖攻略についてちょっとだけそのヒントを書いてみましょうか。そう書くとなんか上から目線ですが、前にも言ったように私とて3回行って1本というペースで釣れるのですから、47年通い続けて何も解っちゃいないので、今年もこうして冬になると通うのですよ。
何度も書いていますが、本栖湖で魚を確実に釣りたいのであれば4月後半〜5月です。この時期は朝はライズしているし、日中はドラワカを楽しんで、1日を通して引っ張りでも釣れるのです。イブニングはライズをドライで狙い撃ちしたり。そんな楽しい本栖湖なんですが、御多分にもれず私も渓流のフライフィッシング好きなので、どうしてもこの時期は鮭鱒類を求めて川へ行ってしまうのです。
ではこの秋から冬に向かっての本栖湖はどうかというと、数は釣れなくてもシャローレンジに刺してくる大物に出会えるチャンスがあるというところでしょうか。毎回朝早くから行っていますが、朝焼けの時間と夕焼けの時間は必ず30分ずつのチャンスがあります。この時間はサイズを問わずなんかしらアタックしてくるので、寒いのを我慢して出撃するんですね。
では昼はどうかというと、基本的には急深部を探してひたすら引っ張りの釣り。もし風が微風で暖かければシャローレンジでドライ撃ちのいずれかでしょうか。よく私に「どこがよく釣れますか?」と質問されますが、私がトラウトを釣ったことがないポイントは、溶岩帯のみなので、どこでも釣れるといって良いでしょう。
溶岩帯は40年以上前にブラウントラウト全盛期の時代に散々通いましたが、人の釣れた話とは裏腹に私が釣ったのは大きなブラックバスだけ。なので、今は溶岩帯だけは行くことが少なくなりました(もちろん、大物をとっている方はいらっしゃいますよ)。
この風と雲の流れならココというポイントは長い経験から思う節はあることはあるのですが、それがいつも思うようにはいかないのです。本栖湖釣り予報を私が出したとしても、釣れる確率が上がるとは到底思えません。やっぱり最後はその場の五感で感じる、第六感(勘または導き出した推測)を信じるしかないんですね。
さて、今回の本栖湖釣行なんですが、前回私は良いサイズを取ることができたので、今回はオデコのつもりで出撃です。あまり事細かに書いてしまうと真似する方が出てくるのでポイントはボヤッと書いておきますが、皆さんも五感を駆使して大物をゲットしてくださいまし。